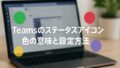色を表すとき、私たちは「赤」「青」「緑」といった言葉を使いますが、業界や用途によってはさらに短縮された2文字の略称やカラーコードで表記されることがあります。
特にデザインやプログラミング、印刷やファッション業界では、効率的で直感的な色管理が求められるため、このような略称は欠かせません。
2文字の表記には簡潔さや視覚的な分かりやすさがあり、チーム間での意思疎通や資料の統一に大きく貢献します。
本記事では、代表的な2文字の色略称からカラーコードの仕組み、実際の活用方法までを詳しくまとめ、色名の略称を効果的に使いこなすための知識を解説します。
色名の略称一覧

2文字の略称の意義と背景
色名を2文字で略す表記は、デザインやプログラミング、印刷業界などで効率的に情報を伝えるために活用されています。
長い色名を簡略化することで、直感的に理解しやすく、作業効率を高める利点があります。
特にデザインの現場では、色をすばやく指定したり共有したりする必要があるため、2文字略称は非常に便利です。
また、2文字略称は色を記号のように扱えるため、データやコード上で扱いやすいのも特徴です。
さらに、グローバルに通じる英語由来の略称が多いため、異なる言語環境のメンバー同士でも認識を合わせやすいというメリットがあります。
学術分野や教育の現場でも、教材や図表においてシンプルな略称が使われることが多く、学習効率を高める役割を果たしています。
代表的な2文字色略称
- RD:Red(赤)
- BL:Blue(青)
- GR:Green(緑)
- YL:Yellow(黄)
- BK:Black(黒)
- WH:White(白)
- GY:Gray(灰)
これらは最も広く使われる略称であり、ファッションや工業製品など幅広い分野で利用されています。
また、これらの基本色以外にも、業界ごとに追加された略称が存在します。
例えば印刷業界では「CY(Cyan)」や「MG(Magenta)」が定着しており、デジタル分野では「OR(Orange)」や「PK(Pink)」などが頻繁に使われています。
略称を統一して使うことで、商品カタログや設計図面、コードベースでの指定がスムーズに行われるのです。
2文字と3文字の略称の違い
2文字略称は短く直感的である一方、3文字略称はより明確に表記できるメリットがあります。
たとえば「GR」はGreenとGrayの両方を意味する可能性がありますが、3文字で「GRE(Green)」「GRY(Gray)」と区別することで混同を避けられます。
特に国際的なやりとりや大量の色を扱う場面では、3文字の方が誤解を避けやすいといえます。
また、ソフトウェアやプログラムの仕様上、略称が固定されているケースもあり、その場合は2文字と3文字を併用することで柔軟に対応しています。
利用シーンや業界の慣習によって、どの形式を採用するかが決められているのです。
2文字略称一覧(アルファベット順)
| 略称 | 英名 | 日本語 |
|---|---|---|
| AL | Aluminum | アルミ |
| AM | Amber | 琥珀色 |
| BK | Black | 黒 |
| BL | Blue | 青 |
| BN | Brown | 茶 |
| BU | Blue (代替) | 青 |
| CH | Charcoal | 炭色 |
| CL / CT | Clear / Clear Transparent | クリア |
| GN | Green | 緑 |
| GY | Gray | 灰 |
| IV | Ivory | アイボリー |
| OG / OR | Orange | 橙 |
| PK | Pink | ピンク |
| RD | Red | 赤 |
| SM | Smoke | スモーク |
| TN / TAN | Tan | タン |
| VT | Violet | 紫 |
| WH | White | 白 |
| YL / YE | Yellow | 黄 |
色名の記号とカラーコード

代表的なカラーコードと色名
カラーコードは、デジタルで色を指定する際に使う16進数の表記方法です。
例えば:
- #FF0000:Red(赤)
- #0000FF:Blue(青)
- #00FF00:Green(緑)
- #FFFF00:Yellow(黄)
- #000000:Black(黒)
- #FFFFFF:White(白)
これらのカラーコードはWebデザインやアプリ開発において基本となるものであり、世界中のプログラマーやデザイナーが共通の基準として利用しています。
また、16進数のRGB表記だけでなく、近年ではHSL(色相・彩度・明度)やRGBA(透過度を含む表記)など、多様な形式での指定も普及しています。
例えば「rgba(255,0,0,0.5)」は半透明の赤を意味し、デザイン表現の幅を大きく広げています。
こうしたカラーコードの活用は、単なる色指定にとどまらず、アクセシビリティを考慮した配色やブランドカラーの統一管理にも役立っています。
2桁のカラーコード利用例
データベースや簡易的な色指定では、2桁の略記を使うこともあります。
例として:
- R1:鮮やかな赤
- B2:濃い青
- G3:淡い緑
このような簡易的な記号化は、特に大量の色を一括管理する必要がある場合や、試作段階で素早くパターンを確認したい場面で効果的です。
例えばアパレル業界のカラーバリエーション管理や、建築設計におけるサンプル提示などで役立ちます。
また、社内規格として2桁コードを独自に定義しておけば、部署や担当者が変わっても一貫した管理が可能となり、作業効率の大幅な向上につながります。
さらに教育分野においても、初心者が色指定の仕組みを理解する導入として2桁コードを使うことがあり、学習のハードルを下げる効果があります。
このように記号化した略称は、大量の色を扱う際に管理しやすくする工夫として活用されています。
色名の略称を使った実例

デザインにおける活用方法
グラフィックデザインやUIデザインでは、カラーパレットを略称で管理することが一般的です。
例えば「BL」を背景色、「RD」をアクセントカラーとして指定することで、制作チーム間の意思疎通がスムーズになります。
また、アパレル業界でもカタログやタグに略称を使い、商品管理の効率化が図られています。
さらに建築やインテリアデザインの現場でも略称が役立ち、図面や設計資料に短いコードを記載することで、誰が見ても直感的に理解できるようになります。
教育の現場では、学生が色彩理論を学ぶ際に略称を利用することで複雑な色の呼称を整理しやすくなり、学習効率の向上にもつながります。
マーケティングでの利用ケース
マーケティング資料や広告デザインでも略称は役立ちます。
ブランドカラーを「BL(青)」として資料内に統一表記すれば、担当者間で色指定を間違えるリスクを減らせます。
さらにSNSの投稿計画表などでも「RD=赤背景」といった略記を使えば、簡潔かつ分かりやすい指示が可能です。
加えて、印刷やパッケージデザインの工程では、略称を共有することで外注先との連携がスムーズになり、ブランドイメージの統一性を保つことができます。
イベントやキャンペーンの企画においても、色略称を活用すれば資料作成やプレゼンテーションが効率化され、社内外での理解度を高める効果が期待できます。
記事のまとめ
色名の略称は、単なる省略ではなく「情報を整理し、効率的に共有するための工夫」として幅広い分野で役立っています。
2文字の略称は直感的で作業スピードを高める一方、3文字略称やカラーコードを使うことで曖昧さを避け、より正確な指定が可能になります。
また、デザインやマーケティングにおいて略称を活用すれば、ブランドカラーの一貫性を保ちながら、誰が見ても理解できる表記ルールを作れるのが大きなメリットです。
略称とカラーコードを状況に応じて使い分けることで、色の管理はシンプルでありながら正確性を高められます。
色は見た目の美しさを決める要素であると同時に、情報を伝える強力な手段でもあるため、略称表記を理解し使いこなすことは、デザインやビジネスの成功につながる重要なポイントといえるでしょう。