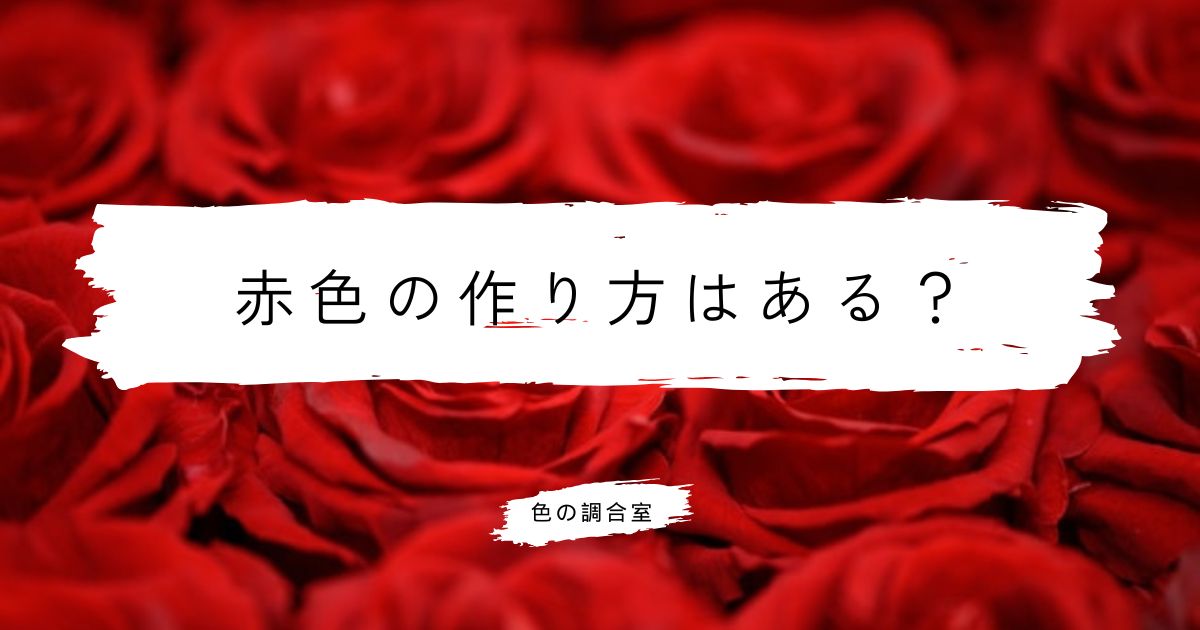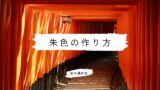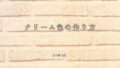赤色は国旗や伝統文化、デザインなどで広く使われる、とても存在感のある色です。
しかし、いざ絵の具で「赤を作りたい」と思っても、他の色を混ぜて純粋な赤を生み出すことはできません。
これは、赤が色の三原色に近い特別な色だからです。
とはいえ、工夫をすれば赤に近い色を再現したり、赤を基準に朱色・ワインレッド・レンガ色といった多彩なバリエーションを作ることは可能です。
さらに、混色に頼らず、色の対比を利用して赤をより鮮やかに見せるテクニックも存在します。
この記事では、赤色を作るための基本原理から混色の具体的な配合、赤色のバリエーション表現までをわかりやすく解説します。
初心者の方でも実践できる方法を紹介していますので、ぜひ参考にして、自分の作品に「理想の赤」を取り入れてみてください。
赤色の魅力と国旗で多用される理由

まずは、赤色という色がそもそもどんな魅力を持ち、なぜ多くの国旗に採用されているのかを見ていきましょう。
この章では、赤色が人の心理に与える効果や、国旗に選ばれてきた歴史的・文化的背景について解説します。
赤色が持つ心理的な効果
赤色は「暖色」の代表格であり、人に暖かみや力強さを感じさせます。
例えば、寒い日に赤いマフラーを見ると少し体感温度が上がるように感じるのも、この心理的効果の一例です。
また、赤は交感神経を刺激し、人を活動的にさせるとされています。
そのため、赤色は気持ちを奮い立たせ、士気を高める色として利用されてきました。
| 赤色の心理的効果 | 具体例 |
|---|---|
| 活力を与える | スポーツウェアや応援グッズに使用 |
| 注目を集める | セールのポスターや信号機 |
| 危機感を伝える | 警告サインや禁止マーク |
国旗に赤色が選ばれる背景
世界の国旗の中で、赤は最も多く使われている色です。
これは、赤が「勇気」「独立」「自由」といった普遍的な価値観を象徴するからです。
また、戦いや革命の歴史を持つ国では、赤を「血」や「犠牲の象徴」として取り入れる場合もあります。
つまり赤は単なる装飾ではなく、国家や民族の想いを込めるための重要な色なのです。
赤色を作ることは可能?

続いて、赤色を自分で作り出せるのかについて見ていきましょう。
この章では、色の三原色の考え方を押さえつつ、赤色が特別視される理由を解説します。
三原色と赤色の関係
絵の具や印刷の世界では、「マゼンタ」「シアン」「イエロー」が三原色とされています。
この三色を基盤にすれば、ほとんどの色を作ることが可能です。
その中で、赤はマゼンタに近い色として扱われます。
ただし、三原色そのものは他の色から作り出せないため、赤色もまた再現が難しいのです。
| 三原色 | 役割 |
|---|---|
| マゼンタ | 赤〜紫の領域を担う |
| シアン | 青〜緑の領域を担う |
| イエロー | 黄色〜緑の領域を担う |
なぜ赤色を他の色から作るのは難しいのか
赤色は鮮やかで明るい特徴を持っていますが、他の色を混ぜて作ろうとすると濁ってしまいがちです。
これは「減法混色」という性質によるもので、絵の具を混ぜれば混ぜるほど暗くなるためです。
結果として、純粋な赤色を再現するのはほぼ不可能といえます。
つまり、赤色の絵の具をそのまま使うのが最も確実で効率的なのです。
赤色を再現する混色の工夫

純粋な赤を他の色から作ることは難しいですが、工夫次第で「赤に近い色」を作ることは可能です。
この章では、絵の具を使って赤色に近づけるための具体的な混色方法を紹介します。
濃いピンクと黄色を混ぜる方法
赤色が手元にないときは、濃いピンクをベースに黄色を少量加えると赤に近づけられます。
例えば、ピンク3に対して黄色1の割合で混ぜると、鮮やかな赤みがかった色になります。
ただし、この方法ではやや明るめの赤になるため、純粋な赤とは微妙に異なります。
身近にある絵の具で工夫して「赤っぽさ」を出せるのが、この方法の強みです。
| 材料 | 割合 | 仕上がりの色味 |
|---|---|---|
| 濃いピンク | 3 | やや明るい赤 |
| 黄色 | 1 |
赤紫と黄色を混ぜる方法
赤紫の絵の具がある場合は、それに黄色を混ぜて赤っぽい色を作ることもできます。
赤紫と黄色を3:1で混ぜると、落ち着いた赤みの色になります。
ただし、マゼンタとは異なるため、完全に鮮やかな赤にはなりません。
絵の具セットに赤紫が含まれている場合に試せる方法ですが、深みのある赤にはならない点に注意してください。
マゼンタとイエローを使った赤色の再現
印刷技術で使われる基本の組み合わせが、マゼンタとイエローです。
マゼンタ自体は赤ではなく紫寄りですが、そこにイエローを加えると赤に近い色を再現できます。
これはプリンターのインクが赤ではなくマゼンタを採用している理由でもあります。
美術用品店でマゼンタとイエローを揃えれば、より自然な赤を作り出せます。
| 材料 | 割合 | 仕上がりの色味 |
|---|---|---|
| マゼンタ | 2 | 鮮やかな赤に近い色 |
| イエロー | 1 |
赤色のバリエーションを作る方法

純粋な赤が手に入れば、それを基準にしてさまざまな色合いを生み出せます。
ここでは、日本で馴染みのある朱色や、深みのあるワインレッド、温かみのあるレンガ色の作り方を紹介します。
朱色の作り方(赤+黄色)
朱色は、神社の鳥居や印鑑の朱肉など、日本文化でよく見られる色です。
赤にごく少量の黄色を混ぜると鮮やかな朱色になります。
ただし、黄色を入れすぎるとオレンジになってしまうため注意が必要です。
黄色を「ほんの少しずつ」足すのが、朱色を成功させるコツです。
| 材料 | 割合 | 仕上がりの色味 |
|---|---|---|
| 赤 | 4 | 鮮やかな朱色 |
| 黄色 | 0.5 |
ワインレッドの作り方(赤+茶+青)
ワインレッドは落ち着きのある高級感を表現したいときに使える色です。
赤に茶色と青を少量ずつ混ぜると、深みのある赤になります。
黒を混ぜると鮮やかさを損なうため、青と茶色でバランスを取るのがポイントです。
赤2:茶1:青1の比率を目安にすると、落ち着いたワインレッドが作れます。
| 材料 | 割合 | 仕上がりの色味 |
|---|---|---|
| 赤 | 2 | 深みのあるワインレッド |
| 茶色 | 1 | |
| 青 | 1 |
レンガ色の作り方(赤+橙+黒)
レンガ色は、赤と橙を混ぜてから、そこに少しずつ黒を足すことで作れます。
茶色に近い赤みの色で、建物や焼き物の表現にぴったりです。
黒を加える量を調整することで、濃いレンガ色から柔らかい色味まで幅広く表現できます。
黒を一度に入れすぎると暗くなりすぎるため、少しずつ足すのがポイントです。
| 材料 | 割合 | 仕上がりの色味 |
|---|---|---|
| 赤 | 2 | 赤茶に近いレンガ色 |
| 橙 | 1 | |
| 黒 | 0.5 |
混色以外で赤く見せる工夫
実際には、赤色を混ぜて作らなくても「赤く見せる」ことは可能です。
ここでは、色の対比や視覚効果を活用して赤を強調する方法を紹介します。
色の対比を利用して赤を強調する方法
色彩学には「補色対比」という考え方があります。
補色とは、色相環(色の並び図)で正反対に位置する色の組み合わせのことです。
例えば、黄色と青紫は補色の関係にあります。
オレンジの周囲に黄色を置くと、黄色が青紫を意識させ、その結果オレンジがより赤っぽく見えるという現象が起こります。
つまり、赤を強調したいときは「隣にどんな色を置くか」が大切なのです。
| 色 | 補色 | 赤が強調される例 |
|---|---|---|
| オレンジ | 青紫 | オレンジが赤寄りに見える |
| 緑 | 赤 | マグロの赤身が鮮やかに見える |
身近な例から学ぶ「赤の見え方」
スーパーのお刺身コーナーで、緑色のしその葉の上に赤身が置かれているのを見たことはありませんか。
これは、緑と赤が補色の関係にあるため、赤身をより新鮮で鮮やかに見せる効果を狙っているのです。
同じ原理で、デザインや絵画でも背景色を工夫することで、赤の存在感を大きく引き出せます。
「混ぜて作れないなら、見せ方で赤に見せる」ことも有効なテクニックです。
まとめ:赤色作りのコツと実践のヒント
ここまで、赤色の性質や混色の方法、そして赤を強調する工夫について解説してきました。
最後に、赤色作りのポイントを整理しておきましょう。
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 赤は三原色に近い色 | 他の色から完全に作ることはできない |
| 赤に近づける混色 | 濃いピンク+黄色、赤紫+黄色、マゼンタ+イエローが有効 |
| バリエーション作り | 朱色・ワインレッド・レンガ色など、赤を基準に多彩に表現できる |
| 混色以外の工夫 | 補色対比を利用して赤を強調する |
赤は単色そのものの力が強い色ですが、工夫次第でさらに魅力を引き出せる色です。
混色で挑戦するのも良し、見せ方を工夫するのも良し。
ぜひこの記事を参考に、自分だけの赤色表現を試してみてください。