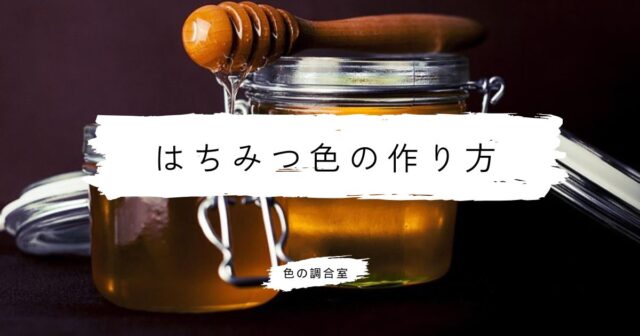はちみつ色は、ただの黄色やオレンジとは違い、自然の恵みをそのまま色にしたような、柔らかく透けるような温もりを持つ色です。
レジンアクセサリーや絵画、デザインにおいても人気が高く、「癒し」「やさしさ」「上品な甘さ」を感じさせる色調として幅広く使われています。
この記事では、そんな魅力的な“はちみつ色”を自分の手で作り出す方法について、絵具、レジン、顔料などさまざまな素材を使った調色レシピを紹介します。
初心者の方でも分かりやすいよう、色の組み合わせのポイントから、透明感やツヤを演出するコツまで丁寧に解説。
ぜひ、あなたの創作にも“とろけるようなはちみつ色”を取り入れてみてください。
はちみつ色とは?

はちみつ色とは、文字通り「蜂蜜」のような透明感のある黄橙色を指します。
まるで自然の恵みを閉じ込めたような、やわらかくてとろみのある色味が特徴で、光を通すことで一層その魅力が際立ちます。
艶やかで奥行きのあるその色合いは、視覚的にも温もりや安心感を与え、見ているだけで心がほぐれるような優しい印象を残します。
この色は、アクセサリーやレジン作品、キャンドル、布小物など、ハンドクラフト全般で非常に人気があり、癒し系やナチュラルテイストの作品にぴったりです。
また、イラストや絵画においても、光が差し込む表現や柔らかいトーンの背景に使われることが多く、色彩バランスにおいても重要な役割を果たします。
さらに、インテリアやパッケージデザインなど商業的な用途でも、親しみやすく落ち着いた印象を与えるため、幅広い分野で重宝されています。
はちみつ色は、その美しさとやさしさから、多くの人に愛され続けている色といえるでしょう。
はちみつ色を作るための基本

はちみつ色を絵の具や着色料で作る際には、基本となるカラーコンビネーションは「レモンイエロー」と「キャラメルブラウン」の2色です。
この2色の配合比率によって、はちみつの種類に見られるような淡いアイボリー系の黄橙色から、濃密なアンバー(琥珀)色まで、さまざまな色調が表現できます。
たとえば、淡いレモンティーのようなはちみつ色を目指すなら、明るいレモンイエローに少量のライトブラウン(ミルクチョコレートのような色)を加えるだけで十分です。
一方、濃厚な百花蜜やアカシア蜂蜜のような色合いを再現したいときは、レンガ色やマルーン(深赤茶)といった赤みのあるブラウンや、スカーレットをほんの少し足すことで、より深みとコクのあるトーンになります。
さらに、ネイビーブルーやスレートブルーをごく微量加えることで、黄味が和らぎ、落ち着きと厚みが生まれます。
これにより、見た目の印象がより自然で洗練されたアンバー系に近づきます。
ただし、ブルー系の色を加えすぎると濁りの原因になるため、極微量から慎重に調整するのがポイントです。
透明感を大切にしたい場合は、クリアメディウムやグロスメディウムを加えると、光を柔らかく反射する艶が出て、よりリアルな「はちみつ感」が生まれます。
また、色の明度や彩度を整えたいときには、ホワイト(パーチメントホワイトやアイボリーホワイトなど)を加えることでトーンを明るくできます。
ただし、これも加えすぎると白濁してしまい、透明感が損なわれるので注意が必要です。
全体として、色味の微調整が仕上がりを大きく左右するため、理想の色合いを得るには段階的に試作しながら調整していくことが重要です。
このように、ほんの少しの配合差で多彩な表情を見せるのが、はちみつ色の奥深く楽しい魅力でもあります。
はちみつ色の作り方 混色レシピ例

- アクリル・水彩などの基本配合
- レモンイエロー(主体)をベースに使用します。これは明るく鮮やかな黄色で、はちみつの明るさと輝きを表現する主役の色です。
- ごく少量のスカーレットを加えることで、色にまろやかな温かみが生まれ、柔らかく自然な黄橙色に仕上がります。
- さらに、極少量のネイビーブルーを加えることで、黄色の鮮やかさが抑えられ、やや落ち着いた琥珀調になります。ブルーは必ず微量にとどめ、色が濁らないよう注意しましょう。
- 最後に必要であれば、少量のアイボリーホワイトを加えると、はちみつ色にやわらかさと濁りのない明度が加わります。
- 和洋絵具の応用例
- 山吹色に近い濃い黄色に、焦げ茶系の色(チョコレートブラウン)または青みを帯びたグレー(スレートグレー)を加えると、重厚感のあるはちみつ色になります。
- この配合では、落ち着いたトーンの和風なはちみつ色や、レトロな印象の黄土色に近づけることができます。
- 最後にパーチメントホワイトなどを加えることで、やわらかな艶感や、透明感を損なわずに明るさを加えることができます。
- また、光沢感が欲しい場合にはグロスメディウムを加えて艶を出すと、レジンやガラス風仕上げにもなじむ色合いに整えられます。
自家製絵具での再現

より本格的には、市販の絵具では得られない風合いや質感を求める人に向けて、黄色系の粉末絵具・アラビアゴム・蜂蜜を組み合わせて自家製の透明水彩絵具を作る方法があります。
作り方はシンプルですが、奥深さがあり、材料の選び方や配合のバランスによって発色が大きく異なります。
まず、明るい黄土のような粉末顔料を選び、これに水で溶いたアラビアゴムを少しずつ混ぜていきます。
次に、粘度と保湿性、そしてなめらかな伸びを加えるために、純粋な蜂蜜を加えます。
この蜂蜜は単なる添加物ではなく、発色の鮮やかさや絵具の柔軟性を高め、乾燥後のヒビ割れを防ぐ役割も担っています。
特に「はちみつ色」を目指す場合、蜂蜜そのものの色味と光沢感が全体の色調に自然な艶を与えるため、素材としての一体感も高まります。
さらに、作った絵具は小皿やパレットに出して自然乾燥させておくことで、固形水彩絵具としても保存が可能です。
再利用時には水を含ませた筆で簡単に溶け、使いたいタイミングでいつでもはちみつ色のぬくもりを再現できます。
このような手作りのプロセス自体も、創作の楽しみの一部として大きな魅力となります。
レジン・インクでの着色法

レジンアートや透明な素材に着色する際には、透明感を損なわずに色を重ねる技術が重要です。
基本的には、透明な明るい黄色をベースにして、少量の赤みのある茶色を丁寧に加えることで、理想的なはちみつ色に近づけます。
このとき、アルコールインクやレジン専用の着色料を使い、色を少しずつ薄く重ねていくのがポイントです。
特に透明な樹脂やガラス風の素材では、色を濃くしすぎると光の透過性が損なわれ、重くくすんだ印象になってしまうことがあります。
そのため、色の調整は慎重に行う必要があります。
一度に多くの色を加えるのではなく、数回に分けて塗布し、少しずつ色味の変化を確認しながら進めることが大切です。
また、着色料を混ぜる際には、グロスメディウムや透明レジンとよくなじませることで、発色が均一になりやすく、ムラのない仕上がりが期待できます。
さらに、完成後にクリアコートや艶出しレジンを上から施すことで、はちみつのようなとろりとした艶感が引き立ち、見た目の美しさがより際立ちます。
このように、レジンやインクを使った着色では、透明感・発色・艶感の3つをバランスよく調整することが成功への鍵となります。
調色の注意点

混ぜすぎず、段階的に色を重ねることが大切です。色を一度に混ぜきってしまうと、濁りやムラが出てしまい、透明感のあるはちみつ色の魅力が損なわれることがあります。筆やパレットナイフを使い、慎重に様子を見ながら少しずつ重ねていくことで、奥行きのある自然な発色が得られます。
明度を調整する際には、柔らかい白(たとえばアイボリーホワイトや淡いベージュ)などを加えてコントロールしましょう。明るさを出したい場合でも、純白を多用すると不自然に白っぽくなるため、淡い色味の白を使うのがポイントです。また、調整のたびに試し塗りをすることで、仕上がりのトーンを把握しやすくなります。
ツヤ感を演出したい場合は、つや出し用のメディウムや透明ニスを併用するのがおすすめです。これにより、はちみつのようなとろみ感や光沢が加わり、視覚的な美しさが引き立ちます。さらに、乾燥後の表面が滑らかになるため、作品の完成度も向上します。
調色の際は、最初から大量に作るのではなく、小量ずつ試作して微調整を行うのが成功のコツです。使った絵の具の種類や比率、重ね方などをメモに残しておくと、後日同じ色を再現したいときに非常に役立ちます。特に手作業での混色は再現性が難しいため、記録を取る習慣が仕上がりの安定性を高めてくれます。
用途別のおすすめ配合

| 用途 | 主な配色 | 特徴 |
|---|---|---|
| アクリル・油彩 | 明るい黄色(ベース)+鮮やかな赤(微量)+深い青(ほんの少し)+柔らかい白(調整用) | 彩度を保ちながらも、深みと透明感を両立できる配色。鮮やかすぎず、自然なぬくもりを演出するには、それぞれの色の分量が重要で、混ぜる順番にも注意が必要です。多層的な塗り方で、蜜のような奥行きを感じさせる作品に向いています。 |
| 日本画・水彩 | 濃い黄色(主体)+焦げ茶(陰影用)+淡い白(明度調整) | 柔らかな発色と落ち着きのある雰囲気を両立できる構成。日本画のように繊細な筆遣いと水加減が必要で、淡いトーンを重ねることで、にじみや光の表現が美しく引き立ちます。季節感や空気感を大切にした作品にぴったりです。 |
| レジン・樹脂 | 明るい黄色(透明)+赤みのある茶色(透明インク)+つや出し用メディウム(必要に応じて) | 透明度の高いレジン作品においては、色の重ね方とインクの濃度が特に重要です。少しずつ薄く重ねることで、ガラスのような透明感を損なわずに奥行きのある色味を再現できます。光の屈折を活かしたデザインに向いています。 |
| 顔料から手作り | 黄色顔料(自然系)+アラビアゴム(水溶性バインダー)+蜂蜜(艶・保湿成分)+必要に応じて柔らかい白 | 手作りだからこそ得られる柔軟な仕上がりが魅力です。顔料の選び方で発色が大きく変わるため、ナチュラルな素材感を活かす調整が必要です。蜂蜜は色味だけでなく、絵具の質感にも影響を与えるため、独自の深みとやわらかさをもたらします。保存や再利用もしやすく、作品の表情が豊かになります。 |
「はちみつ色」は単なる色の名前以上に、素材の質感や光の演出とも密接に関わる奥深い表現であり、それぞれの用途や技法によって、最適な色の組み合わせとアプローチが変化します。
記事のまとめ
はちみつ色は、単なる黄橙色ではなく、光を柔らかく包み込むような温かみと、見る人をほっとさせる癒しの質感を持った色です。
そのため、混色によって再現する際には「色味」だけでなく「質感」や「透明感」も同時に意識することが重要になります。
基本となる色構成は、明るい黄色を主軸に、少量の鮮やかな赤や深い青、落ち着いた茶色などを加えることで調整できます。
たとえば、レモンイエローに少量のチェリーレッドとネイビーブルーをほんの少し混ぜることで、鮮やかで深みのある黄金色が作れますし、より柔らかくナチュラルに仕上げたい場合は、焦げ茶や青みのあるグレーのような穏やかな補色を加えるのも効果的です。
また、顔料から自作する場合には、アラビアゴムや蜂蜜を加えることで、しっとりとした艶感や柔軟性を持たせることが可能となります。
蜂蜜は色味だけでなく、絵具全体にやわらかさと滑らかさを与えるため、より自然で深みのある色合いを引き出してくれます。
レジンアートにおいては、透明度の高い黄色や茶色系のインクを使いながら、色を少しずつ丁寧に重ねていくことで、理想の“蜂蜜のような透明感”を表現することができます。
透明感を活かした層状のグラデーションや、光の反射を計算した濃淡のつけ方など、テクニックの工夫によって奥行きのある作品に仕上がります。
このように、はちみつ色の調色にはいくつかのアプローチがありますが、いずれの方法でも「少しずつ試す」「配合を記録する」「光との相性を確認する」といった工程が、成功への近道となります。
たとえほんの数滴の違いであっても、最終的な雰囲気や印象ががらりと変わるのが、この色の持つ繊細な魅力の一部なのです。
創作活動において、“はちみつ色”は甘さと品の良さを兼ね備えた、非常に万能で応用の利くカラーです。
自然を感じさせるナチュラルな表現が求められる場面や、落ち着きと癒しを伝えたい場面でぜひ活用してみてください。
きっとあなたの作品に、優しくあたたかな彩りを添えてくれるはずです。