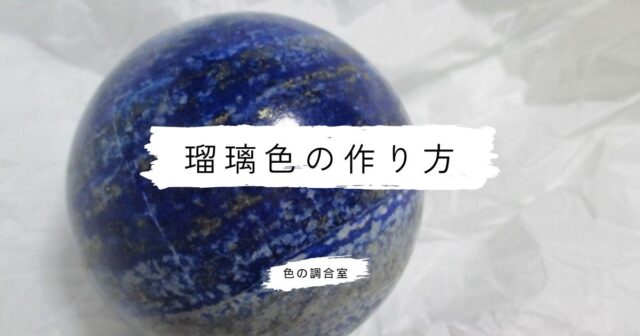深い海のような青、夜明け前の空に似た神秘的な色──それが「瑠璃色」です。
日本の伝統色のひとつでもあり、落ち着きと品格を感じさせる瑠璃色は、多くのアート・デザインシーンで重宝されています。
この記事では、「瑠璃色ってどう作るの?」「鮮やかに見せるにはどうすればいい?」といった初心者の方の疑問に応えるべく、絵の具や顔料の選び方から混色のテクニック、さらにはデザインでの活用例まで、実践的かつやさしく解説します。
少ない道具でもOK。
青の深みをコントロールしながら、あなたらしい瑠璃色を自在に作れるよう、ステップバイステップでナビゲートしていきます。
初心者でもできる瑠璃色の作り方

瑠璃色とは?その特徴と魅力
瑠璃色は、深みのある青紫に近い色で、日本の伝統色の中でも特に高貴さと静けさを感じさせる色です。
もともとは天然の宝石「ラピスラズリ」の色から由来しており、古くから染織や工芸、仏教美術などにも多用されてきました。
ラピスラズリはかつて非常に貴重で、粉砕して絵の具にすることでしか得られなかったため、特別な場面でのみ使われていた色でもあります。
その魅力は、単なる青ではなく、わずかに紫がかった深みのあるトーンにあります。
洗練されていながらも、やさしく落ち着いた印象を与えることができるため、現代でもファッション・グラフィック・プロダクトデザインなどで重宝されています。
また、瑠璃色は視覚的な安心感を与える色として、インテリアやブランドカラーなどにも取り入れられやすく、上品でありながら記憶に残りやすいのが特徴です。
西洋では「ロイヤルブルー」と呼ばれる色と通じる点があり、東西を問わず格式や気品を象徴するカラーとして高く評価されています。
日本の四季の中では特に冬や早春にマッチし、雪景色や夜空といったモチーフとも相性が良いとされます。
必要な絵の具と顔料の紹介
瑠璃色を作るための基本となる絵の具は以下の通りです:
- ウルトラマリンブルー(青のベース)
- バイオレットまたはマゼンタ(紫みを加える)
- 白(明度調整用)
- 黒またはグレー(深みを加える)
これに加え、天然顔料を扱いたい場合は、ラピスラズリ系の顔料(高価)や合成ウルトラマリンもおすすめです。
特に日本画では群青や岩絵具のような天然顔料が使われ、独特の発色と奥行きを表現することができます。
アクリル絵の具や油彩用の顔料としてもさまざまな瑠璃系ブルーが展開されているため、画材のバリエーションに合わせて選ぶことが可能です。
瑠璃色の彩度と明度について
彩度とは色の鮮やかさ、明度とは色の明るさを指します。
瑠璃色は中〜高彩度・中〜低明度のバランスが魅力。
鮮やかにしすぎると「紺碧」寄りになり、明るくしすぎると「スカイブルー」に近づいてしまうため、適度な深みを保つことが重要です。
深みのある色調を保ちつつも、やや鮮やかな色味を出したいときには、明度を変えずに青とバイオレットの比率を調整するのが有効です。
混色の際には、バイオレットや黒を加えることで彩度を保ちつつ暗さを出すのが効果的です。
グレーや茶系の絵の具をほんの少し加えることで、より落ち着いたトーンに調整することもできます。
こうした調整によって、季節感や使用シーンに合わせた色づくりが可能になります。
色相の理解と瑠璃色の調整
色相環を参考にすると、瑠璃色は「青」〜「青紫」ゾーンに位置します。
純粋な青をベースに、赤系の色を少量足すことで、より伝統的な瑠璃色に近づきます。
目的に応じて、紫寄り・青寄りの調整を試してみましょう。
色相を変化させるときには、使う絵の具の透明度や顔料の濃さにも注目しましょう。
同じバイオレットでもメーカーや顔料の違いで仕上がりが大きく変わります。
複数の青や紫を試してみることで、より自分の理想とする瑠璃色に近づけることができます。
瑠璃色の基本的な調合方法
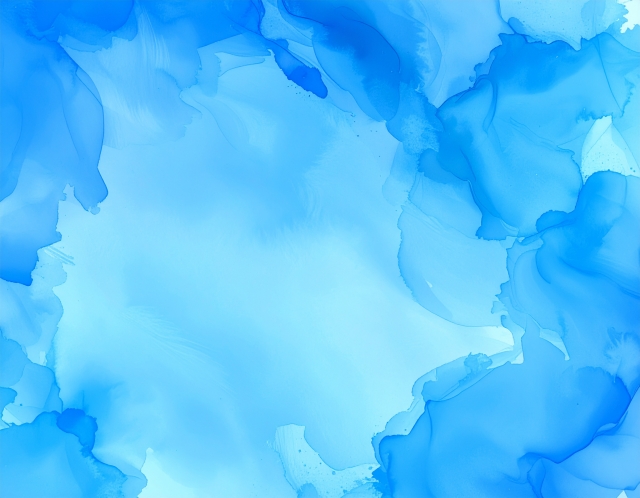
青色のベースを作る
まずは、ウルトラマリンブルーを中心にベースカラーを作ります。
ウルトラマリンブルーはやや紫がかった青で、瑠璃色の土台として最適です。
透明水彩の場合は、たっぷりの水を使って軽く広げることで、色の重なりによる深みが出やすくなります。
また、水の含み具合や紙の質感によって発色が変わるため、何度かテストしてベストな塗り方を探すのがポイントです。
このベースに、必要に応じてバイオレット系の色を少量ずつ加えていきます。
加える量を慎重に調整することで、青すぎず、紫すぎず、ちょうどよい“瑠璃色”に仕上がります。
さらに、筆のタッチや塗り重ねる回数によっても発色に違いが出るため、柔らかなグラデーションを意識してレイヤーを重ねていきましょう。
ホルベイン絵の具を使った瑠璃色
ホルベインの「コンポーズブルー」や「ミネラルバイオレット」は瑠璃色の再現におすすめの色です。
これらをベースに調整することで、少ない混色で効率的に近い色を作ることができます。
特に、絵の具に不慣れな初心者には、あらかじめ調整された中間色を用いることで色の失敗が少なくなり、気軽に取り組みやすくなります。
ホルベインの色は発色が良く、透明度が高いため、透明水彩やグラデーション技法とも相性が抜群です。
必要に応じて、白やグレーを加えて明度調整したり、補色を少し加えて彩度を落ち着かせることで、より洗練された印象の瑠璃色に仕上げることができます。
彩度を調整するためのテクニック
混ぜすぎは彩度を下げる原因になるため、絵の具は少しずつ加えるのがコツです。
赤や茶系を足すことで色がくすんでしまう場合は、青をやや多めにしてクリアな印象を保つと良いでしょう。
理想的な彩度を保つためには、最初から強く混ぜず、必要に応じて段階的に色を加えていく方法が推奨されます。
また、彩度が下がりすぎた場合は、透明感のある青を少し足してリセットすることも可能です。
さらに、紙の色が背景として作用するため、白い紙を使うことで彩度の高い色をより鮮やかに見せることができます。
塗り重ねの順序や筆の含み具合など、工程全体を意識することでより高彩度な瑠璃色を表現できます。
明度の調整方法とコツ
明度を上げたい場合は白を、下げたい場合は黒またはペインズグレーを加えます。
ただし、白を多くするとミルキーで不自然になることもあるため、数回に分けて加えて微調整するのが理想です。
微調整を繰り返すことで、自然な色の階調を作り出すことができ、作品全体のクオリティが向上します。
明度の調整には、グレーや紫みを帯びた色を活用するのも効果的です。
白だけで明るくしようとせず、絵の具本来の持つ色味を活かすことで、透明感のある美しい瑠璃色が完成します。
異なる瑠璃色のバリエーション
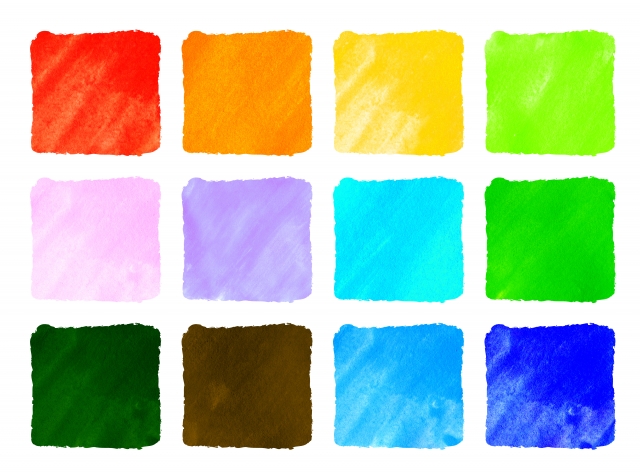
彩度が高い瑠璃色
ウルトラマリン+マゼンタを明度調整なしで混ぜると、鮮やかな高彩度の瑠璃色が完成します。
特にウルトラマリンブルーの発色とマゼンタの赤みが絶妙に混ざり合うことで、光沢感のあるリッチなブルーが得られます。
彩度が高いため、ポスターや広告、ウェブバナーのように注目を集めたいシーンで非常に効果的です。
また、印刷物やディスプレイなどのRGB/CMYK調整にも応用が効きます。
このタイプの瑠璃色は、インクやビーズ、ガラスなど光を反射する素材と組み合わせることで、より一層の輝きが増します。
高彩度ながらも品のある印象を保つためには、他の色とのバランスや面積比を調整することが重要です。
明度が低い瑠璃色の作り方
同じ配色に黒や濃いグレーを加えると、深みのある低明度の瑠璃色になります。
暗くしすぎずに重厚感を演出するには、黒をほんの少量ずつ加えながら調整していくのがポイントです。
この手法で作られた瑠璃色は、夜景の背景、クラシックな書籍装丁、ブランドの高級感演出などに多用されます。
また、低明度な瑠璃色は精神的な落ち着きや静寂、荘厳さを演出するため、室内のインテリアや舞台照明の基調にも適しています。
色の深さにムラがあると味わいも生まれやすく、手作業による重ね塗りにも向いています。
デザインに合った瑠璃色の選び方
ブランドロゴ、背景、和風パッケージなど、用途に応じて彩度・明度のバランスを調整しましょう。
冷たい印象にしたい場合は青寄りに、あたたかみを出したい場合は紫寄りに寄せると印象が大きく変わります。
たとえば、技術やIT系企業には青寄りのクリアな瑠璃色が適しており、文化・工芸や伝統分野では紫寄りで落ち着いたトーンが好まれます。
使用する場面に合わせて、マット系・グロス系など素材の質感も考慮することで、瑠璃色の印象がさらに引き立ちます。
印刷・デジタル・テキスタイルといった表現媒体の違いを考慮しながら、最適な瑠璃色を導き出していきましょう。
まとめ
瑠璃色は、単なる「青」では表現しきれない奥行きと繊細さを持つ魅力的な色です。
この記事では、絵の具の選び方から混色テクニック、デザインへの応用例、さらには保存・管理方法まで、初心者でも再現しやすい手法でわかりやすく解説しました。
絵の具を混ぜながら、思い通りの色にたどり着くまでのプロセスは、まさに創作の醍醐味です。
色をつくる楽しさは「試行錯誤の中にこそある」と言われるように、瑠璃色もまたあなた自身の感覚で育てていける色です。
混色のちょっとした違いが大きな印象の変化を生むことに気づけば、色彩表現への理解が一段と深まるはずです。
まずは紹介した方法をベースに、あなただけの“深い青”を探し、何度も試して調整してみてください。
たとえ理想の色にたどり着くまでに時間がかかったとしても、その過程すらも作品の一部として楽しんでみてください。
きっと、あなたの感性と手仕事によって、作品に静かな輝きを与える、唯一無二の瑠璃色が生まれるはずです。
そしてその色は、あなたの表現をより一層魅力的に、そして記憶に残るものにしてくれるでしょう。