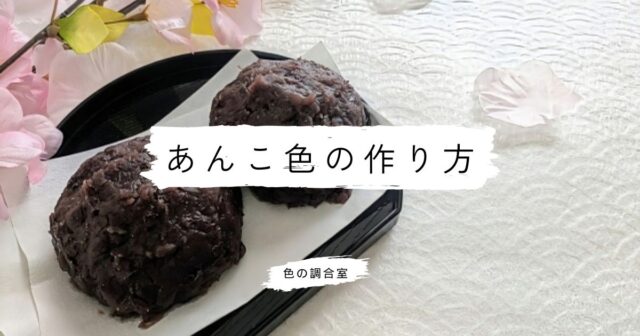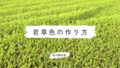あんこ色は、和の雰囲気を持つ落ち着いた色合いのひとつであり、赤みを帯びた茶色として日本の伝統色に分類されます。
本記事では、そのあんこ色を絵の具でどのように作り出すか、さまざまな視点から徹底的に解説していきます。
色彩の配合だけでなく、表現方法、調整のポイント、さらには他の画材やデジタルでも応用できる知識まで、幅広く網羅しています。
あんこ色を作ることは単に色を混ぜるだけではありません。
その色に含まれるニュアンスや温かみ、奥行きを正しく理解し、繊細に表現する力が求められます。
初心者の方でも安心して取り組めるよう、配合例や失敗時のリカバリー方法なども丁寧に紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
あんこ色の定義・作り方とは

あんこ色の定義と特徴
あんこ色とは、小豆(あずき)を煮詰めて作った餡(あん)に似た、深みのある茶色がかった赤色を指します。
和菓子に使われるこしあんやつぶあんの色味に近く、どこか懐かしさや温もりを感じさせる色合いです。
日本の伝統色のひとつにも分類されることがあり、落ち着いた印象と上品さを兼ね備えています。
デザインやアートに取り入れることで、和の雰囲気や季節感を演出することができます。
あんこ色を作るための基本材料

あんこ色を再現するために使う基本絵の具
あんこ色を絵の具で再現するには、主に以下の三色が基盤になります。
- ブラウン(茶色):この色があんこ色の土台になります。柔らかい茶系の色合いで、赤系の色を乗せたときに自然な深みが生まれやすいです。絵の具の種類によっても発色が異なるため、自分の使っているブランドでのブラウンの傾向を知っておくと調整しやすくなります。
- レッド(赤):ほんのりと赤みを加えることで、単なる茶色ではない独特の色合いになります。特に和の雰囲気を意識する場合は、ややくすんだレッドやワインレッド系を使うと、あんこのような落ち着いた赤みが表現できます。
- ブラック(黒):深みと落ち着きを与えるためにごく少量使用します。加えすぎると色が暗くなりすぎてしまうため、ほんのひと筆分からスタートするのが基本です。特に絵の具が乾いた後に黒が強く出ることがあるため、試し塗りも忘れずに行いましょう。
これらの色を少しずつ混ぜて調整することで、好みに合わせた“あんこらしさ”を演出できます。
微妙な配色の違いで印象が大きく変わるため、最初は少量ずつ試しながら混ぜるのがコツです。
また、乾く前と乾いた後で色味が若干変わるため、完成後の色の見え方を意識して調整することも大切です。
何度か練習して、自分にとって理想的な“あんこ色”のバランスを探してみましょう。
あんこ色の具体的な作り方

濃いあんこ色の作り方
- ブラウンをベースにたっぷりと出します。量的には全体の約70%を占めるくらいでよいでしょう。ブラウンはあんこ色の基本となる土台の色なので、ここでしっかりとした色味を出すことが重要です。質感としては、マット系のブラウンの方があんこ色らしい落ち着きを表現しやすくなります。
- レッドを少量加え、赤みをプラスします。全体の20〜25%程度が目安です。赤を足すことで、あんこ特有の赤茶っぽい色味が際立ち、温かみや柔らかさが出ます。明るめのレッドよりも、やや深めのワインレッドやレンガ色寄りのトーンを選ぶと、よりリアルなあんこ色に近づきます。
- ブラックをほんのわずか(ごく少量)足して、深みと渋みを出します。全体の5〜10%程度が適量です。ブラックの入れすぎには要注意で、色が重くなりすぎてしまうと、泥色に近づいてしまう恐れがあります。調整は慎重に行いましょう。
配合目安:ブラウン7:レッド2:ブラック1
黒を入れすぎると全体が重たく、くすんだ印象になるため、最初はほんの少量から試すのがおすすめです。
また、黒は乾くとさらに強く出る傾向があるため、調整中は必ず試し塗りをして確認すると安心です。
薄いあんこ色の作り方
濃いあんこ色をベースに、水または白(ホワイト)を加えて色味を明るく調整します。
淡いトーンのあんこ色は、和菓子の中でもやわらかい餡の雰囲気を再現するのに適しています。
- 水を加えることで、透明感のある軽やかなあんこ色に。水彩絵の具やアクリル絵の具を使う場合、水での調整がしやすく、にじみやグラデーションも表現できます。
- 白を加えることで、やわらかくミルキーな印象のあんこ色になります。ポスターカラーや不透明水彩を使っているときは、白を混ぜることで均一で柔らかな質感になります。
ただし、白を加えすぎると赤紫やピンクに寄ってしまうため、少しずつ様子を見ながら加えるのがポイントです。
また、白の絵の具の種類(ウォームホワイトかクールホワイトか)によっても仕上がりが微妙に変わるので、色の温度感にも気を配ると良いでしょう。
微調整で理想のあんこ色に仕上げるコツ
あんこ色は人によって「濃い目が好き」「赤っぽい方が好み」といった好みが分かれます。
そのため、以下のような調整法を覚えておくと便利です。
- 赤みを強めたいとき:レッドを少しずつ追加。特に赤系の餡子に近づけたい場合は、深めの赤を重ね塗りすると印象がはっきりします。
- 深みをもっと出したいとき:ブラックを極少量追加。黒を使うことで色に重みと渋みが加わり、大人っぽく洗練された仕上がりになります。
- 落ち着きすぎた印象を和らげたいとき:ブラウンを足してバランスを取る。色が暗くなりすぎたときに全体をリセットする効果があります。
絵の具を混ぜる際は、一度にたくさん混ぜるのではなく、筆先やパレットナイフなどで少しずつ様子を見ながら調整するのがコツです。
試し塗りをこまめに行い、乾いた後の色味の変化もチェックすると、仕上がりに満足できるあんこ色に近づけます。
カラーコードとあんこ色の関係

あんこ色に対応するカラーコード一覧
Webカラーコードの中には、あんこ色に近い色味として以下のようなものがあります。
- #7B3B3B:深みのある赤茶。濃いめのこしあんに近い色。やや黒みを帯びた落ち着いた赤茶色で、和風の上品さを演出するのに適しています。重厚な印象を与えるため、背景色やアクセントカラーとしても使いやすいです。
- #8B5C5C:やや明るめで、つぶあんを意識したような柔らかな赤茶。赤みがやや強めで、温かみを感じさせる色合い。主張しすぎず、他の色ともなじみやすい万能なトーンです。
これらのカラーコードは、WebデザインやDTPの配色にも応用可能で、あんこ色をデジタルで扱いたいときに便利です。
また、トーンを調整することで、和モダンなテイストやナチュラルな雰囲気など、幅広いイメージに対応することができます。
背景や文字のアクセントとして使う場合、コントラストとのバランスにも注意するとよいでしょう。
色鉛筆や他の画材での再現方法
絵の具以外の画材でもあんこ色は再現可能です。たとえば:
- 色鉛筆:ブラウン系をベースに、レッド系を上から重ねて塗ると近い雰囲気になります。色を重ねる際は、塗りの強弱を意識することで、自然なグラデーションが出やすくなります。
- パステル・クレヨン:混色が難しい画材ですが、茶系と赤系を重ねる、または混ぜることで表現できます。パステルの場合は指でなじませることで柔らかな質感が出せますし、クレヨンなら少し硬めの紙を使うと発色がきれいです。
- デジタルイラスト:RGBやHEXでカラーコードを指定すれば、簡単に再現可能です。さらに、デジタルでは色の透明度や光の当たり方などを自由に調整できるため、あんこ色のもつ繊細なニュアンスをより詳細に表現できます。アプリによっては、和色パレットを取り入れたプリセットが用意されていることもあるので、そうした機能も活用しましょう。
あんこ色作成のQ&A
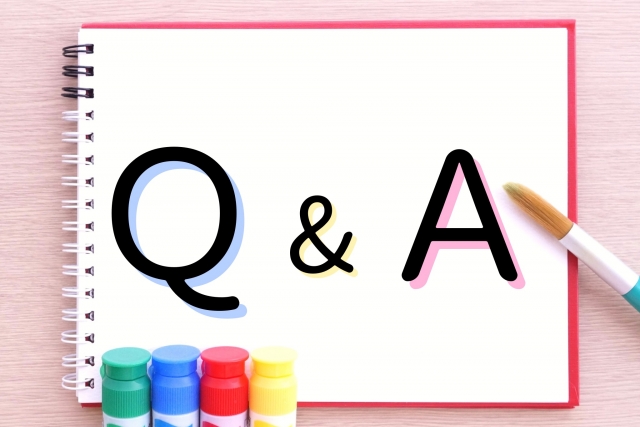
よくある失敗とその対処法
- 黒くなりすぎた場合:ブラックを入れすぎると色が沈みすぎてしまいます。その場合は、まずブラウンを多めに加えて土台の明るさを取り戻しましょう。その後、必要に応じてレッドを少しずつ足して、あんこ色の赤みを再調整します。また、使用するブラックが濃すぎる場合には、代わりにグレー系の中間色を加えるという工夫も有効です。調整前と後の色を見比べながら、慎重にバランスを取っていきましょう。
- 赤すぎる場合:レッドが多いと鮮やかすぎる赤茶色になり、和風の落ち着いた印象が薄れてしまいます。この場合、まずブラウンを少しずつ加えて中和することで、色を落ち着かせます。もしそれでも明るすぎると感じた場合には、ごく少量のブラックを足すことで渋みが増し、全体の調和がとれます。混色を繰り返すことで自分好みの赤茶色に近づけることが可能です。
- 色がぼやける場合:彩度が足りない、または混ぜすぎて濁ってしまった場合、少しだけブラックを加えると色が締まりますが、それ以外にも補色(反対色)を意識するのも効果的です。例えば、彩度を高めたいときには、少量の赤紫や深い青系の色を足すことで印象が引き締まることがあります。また、色を塗る紙の質感や絵の具の乾き具合も最終的な発色に影響するため、テスト用紙で何度か試すことをおすすめします。
あんこ色に関するよくある質問
Q. 直接あんこ色の絵の具は売っていないの?
A. 一部の画材メーカーで「和色シリーズ」などに含まれている場合もありますが、基本的にはあんこ色専用の単体絵の具は流通していません。
そのため、自分で配合して作るのが一般的です。
好みに応じて微調整できる点も、自作の魅力です。
市販の絵の具セットを活用して、少しずつ練習しながら自分だけの配合バランスを見つける過程もまた、創作の楽しさの一部となります。
まとめ
この記事では、あんこ色という日本の伝統的な色味を、絵の具でどのように再現できるかを詳しくご紹介しました。
あんこ色は単なる茶色ではなく、赤みと深みを併せ持つ独特のトーンであり、その繊細さゆえに再現には工夫と経験が必要です。
ほんの少しの色の比率を変えるだけでも印象が大きく変わるため、各工程で慎重な調整が求められます。
濃いあんこ色、薄いあんこ色、さまざまな色のバリエーションを出すための配色バランスや微調整のテクニックを身につければ、自分だけの表現が可能になります。
特に、自分の使う絵の具の種類や紙質によっても、仕上がる色合いは微妙に異なるため、同じ配合であっても結果が変わることがあります。
色の見え方は照明の条件や周囲の色によっても影響を受けるため、異なる環境下での確認も大切です。
そうした細かな観察力と実験の繰り返しが、色作りのスキルを向上させてくれます。
さらに、デジタルカラーコードや色鉛筆など、他の画材でも応用可能な方法を知っておくことで、アナログとデジタルの両方で自由にあんこ色を活用できるようになります。
デザインやイラスト、工芸などさまざまな場面で役立てることができるあんこ色の知識は、創作活動を豊かにしてくれることでしょう。
この記事が、自分だけの“あんこ色”を見つけたい方にとって、確かな手引きとなれば幸いです。