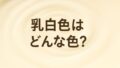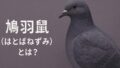日本の伝統色の中でも、どこか懐かしく優しい赤として知られる「甚三紅(じんざもみ)」。
この色は、江戸時代に庶民が高価な紅花染めの代わりとして生み出した、蘇芳による紅色です。
紅花の華やかさとは異なり、少し黄みを帯びた柔らかい赤が特徴で、派手すぎず心を穏やかにしてくれます。
この記事では、甚三紅の由来や歴史、色コード(RGB・CMYK・Webカラー)をはじめ、紅梅色や蘇芳など関連する色との違いを詳しく紹介します。
江戸の人々が生み出した「日常の美」を、今のデザインにどう活かせるのか。
和の心を感じる赤の世界へ、一緒に触れていきましょう。
甚三紅(じんざもみ)とはどんな色?

ここでは、日本の伝統色「甚三紅(じんざもみ)」の基本情報と、その歴史的な背景を解説します。
色名の由来や色合いの特徴を知ることで、江戸時代の文化や美意識の一端が見えてきます。
甚三紅の基本データ(RGB・CMYK・Webカラー)
甚三紅は、紅花を使わずに蘇芳(すおう)で染めた紅色で、黄みがかった落ち着いた赤色です。
デジタル表現の際は、以下のような色コードが基準になります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| RGB | R:210 / G:63 / B:64 |
| CMYK | C:0 / M:85 / Y:64 / K:15 |
| Webカラー(Hex) | #D23F40 |
| 誕辰色 | 3月18日 |
この色は、デジタル環境でも再現しやすく、現代のデザインにおいても活用しやすい日本の伝統色のひとつです。
やや黄みを帯びた柔らかな赤が、華やかさと落ち着きを兼ね備えています。
名前の由来と歴史的背景
「甚三紅(じんざもみ)」という名前は、江戸初期の承応年間(1652〜1655)に京の染屋「桔梗屋甚三郎(ききょうやじんざぶろう)」が生み出したことに由来します。
紅花を使わずに「紅梅色(こうばいいろ)」のような絹布を染め出したことから、この色名が生まれました。
当時、紅花を使った染色は高価で、庶民には手の届かないものでした。
しかし、蘇芳を使った甚三紅は安価に染められるため、多くの人々に受け入れられたのです。
「紅花の贅沢を、蘇芳で再現した庶民の知恵」とも言える色なのです。
| 時代 | 出来事 |
|---|---|
| 1650年代(承応年間) | 京の桔梗屋甚三郎が代用染めを考案 |
| 江戸時代 | 紅花染めの禁制により、蘇芳による染色が普及 |
| 以後 | 甚三紅として庶民文化に根付く |
この色の誕生は、単なる染色技術ではなく、江戸の人々の生活感覚や美意識の象徴でもあります。
甚三紅の誕生と庶民文化

江戸時代の人々にとって、華やかな紅色は憧れの色でした。
しかし、紅花を使った染色は高価で、贅沢品として度々幕府によって禁制とされました。
そんな中で登場したのが、庶民の味方「甚三紅」です。
江戸時代の禁制と代用染めの工夫
紅花による染めは、その美しさゆえに上流階級の象徴でもありました。
幕府は贅沢を戒めるため、紅花を使った衣服を禁止することもありました。
一方で、蘇芳(すおう)は東南アジア原産のマメ科の植物で、木片を煮出して赤い染料を得ることができます。
この蘇芳を用いることで、紅花に似た赤をより安価に表現できたのです。
| 染料 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|
| 紅花 | 鮮やかな赤色、退色しやすい | 非常に高価 |
| 蘇芳 | ややくすんだ赤、耐久性がある | 比較的安価 |
蘇芳を使った代用染めは、経済的でありながら美しさを保つ庶民の知恵でした。
庶民に愛された理由
甚三紅は、ただの代用品ではありませんでした。
黄みを帯びた穏やかな赤は、華やかすぎず、日常に溶け込む上品さを持っていました。
また、紅花のように色が早く褪せることも少なく、実用性の面でも高く評価されました。
| 特徴 | 庶民に好まれた理由 |
|---|---|
| 手頃な価格 | 紅花より安く入手可能だった |
| 落ち着いた色合い | 普段着にも合わせやすい |
| 長持ちする色 | 退色しにくく、丈夫だった |
庶民の生活と感性に寄り添った「経済と美のバランス」が、甚三紅の人気を支えたのです。
この色は、倹約の時代にも心の豊かさを求めた日本人の美意識を映しています。
甚三紅の色味と印象

ここでは、甚三紅の色の特徴や心理的な印象、そして現代のデザインにおける活用方法について解説します。
紅花との違いや黄みがかった独特の色味を理解することで、この色がもつ美的魅力をより深く味わうことができます。
紅花との違いと特徴的な黄みの色合い
紅花による染めは、鮮やかでやや青みを帯びた赤が特徴です。
一方で、甚三紅は蘇芳を用いたため、やや黄みを帯びた温かみのある赤色となります。
そのため、見る人に穏やかで落ち着いた印象を与えます。
| 染料 | 色味の特徴 | 印象 |
|---|---|---|
| 紅花 | 青みのある鮮やかな赤 | 華やか・高貴 |
| 蘇芳(甚三紅) | 黄みを帯びた落ち着いた赤 | 温かみ・穏やかさ |
このわずかな黄みの差が、甚三紅をより「日常の赤」にしているのです。
華美ではないのに印象に残る――それが甚三紅の最大の魅力です。
心理的イメージと現代デザインでの活用
赤色は一般的に「情熱」「生命力」「喜び」を象徴します。
しかし、甚三紅のように黄みを含む赤は、より「安心感」「やさしさ」「人の温もり」を感じさせます。
現代のデザインにおいては、伝統的でありながらモダンな印象を与える色として、和のインテリアやブランドロゴにも採用されています。
| 利用シーン | 効果 |
|---|---|
| 和風ロゴ・パッケージ | 伝統と上品さを演出 |
| インテリア(襖・障子・壁紙) | 落ち着きと温かみをプラス |
| ファッション | 肌なじみがよく、季節を問わない |
甚三紅は「主張しすぎず、心に残る赤」として現代でも息づいています。
甚三紅に関連する伝統色

甚三紅は単独で美しいだけでなく、他の日本の伝統色との関係性を知ることで、その位置づけや個性がより明確になります。
ここでは、特に関連の深い「紅梅色」「蘇芳」「紅色」との違いを見ていきましょう。
紅梅色との関係
紅梅色(こうばいいろ)は、紅花によって染めた淡い紅色です。
その名の通り、梅の花のような明るく華やかな色合いが特徴です。
甚三紅は、この紅梅色を蘇芳で代用しようとしたことから生まれたといわれています。
| 色名 | 色味 | 特徴 |
|---|---|---|
| 紅梅色 | 淡く明るいピンク系 | 上品で女性的 |
| 甚三紅 | やや黄みがかった落ち着いた赤 | 温和で庶民的 |
紅梅色が「春の華やかさ」を象徴するなら、甚三紅は「日常の温もり」を象徴する色です。
蘇芳との違い
蘇芳(すおう)は、甚三紅のもとになった染料の名前でもあり、より深く赤みを帯びた色です。
蘇芳色はやや紫みがかり、格式高い印象を与えます。
一方の甚三紅は、蘇芳の色を薄めたような柔らかさが特徴で、より親しみやすい印象を持ちます。
| 色名 | 色味 | 印象 |
|---|---|---|
| 蘇芳 | 紫みのある深紅 | 重厚・高貴 |
| 甚三紅 | 明るく黄みがかった赤 | 穏やか・庶民的 |
甚三紅は、蘇芳の「格調」と紅梅色の「可憐さ」を併せ持つ色と言えるでしょう。
紅色(すおう)との比較表
ここでは、紅花で染めた紅色との違いを一覧で整理します。
これを見ると、甚三紅がいかに独自の位置を占めているかが分かります。
| 色名 | 主な染料 | 色味 | 印象 |
|---|---|---|---|
| 紅色 | 紅花 | 鮮やかな赤 | 高貴・華やか |
| 甚三紅 | 蘇芳 | 黄みがかった赤 | 穏やか・温かみ |
紅色が「上層の華やかさ」なら、甚三紅は「下町の粋」を体現しています。
この比較が示すように、甚三紅は日本の色文化におけるバランスの象徴なのです。
甚三紅のまとめと現代への継承
ここでは、甚三紅という色が現代にどのように受け継がれているのかを見ていきます。
江戸の庶民文化に根付いたこの色は、今もなお日本人の感性の中で生き続けています。
現代のファッション・アートでの再評価
最近では、伝統色を現代のデザインに取り入れる動きが高まっています。
中でも甚三紅は、過度な主張をしない自然な赤として、多くのクリエイターに注目されています。
例えば、和のブランドロゴや、落ち着いたトーンのファッション、パッケージデザインなどに用いられています。
| 分野 | 活用例 |
|---|---|
| ファッション | 和モダンなワンピースや小物のアクセントカラー |
| グラフィックデザイン | 日本文化を想起させるブランドロゴや名刺デザイン |
| アート・建築 | 伝統と現代を融合させた空間演出 |
甚三紅は「過去を語る色」でありながら、「今を彩る色」としても生き続けています。
伝統色を学ぶ意義
日本の伝統色は、単なる色名の集まりではありません。
そこには、時代背景や人々の暮らし、思想、美意識が深く刻まれています。
甚三紅のような庶民の知恵から生まれた色を知ることは、日本の文化の多層性を理解することでもあります。
| 学びの視点 | 得られる気づき |
|---|---|
| 歴史的背景 | 江戸庶民の価値観や生活文化を知る |
| 色彩感覚 | 「華やかさ」ではなく「調和」を重んじる日本的美意識 |
| 現代応用 | 伝統を活かした新しいデザイン発想 |
伝統色を知ることは、過去を懐かしむためではなく、未来を創るためのヒントを得ることなのです。
甚三紅は、時代を超えて「心のぬくもり」を伝える日本の赤の象徴です。