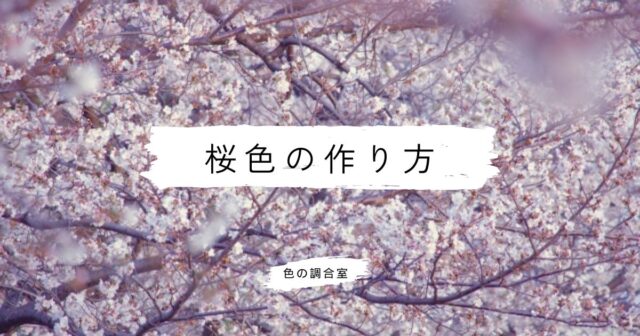春といえば桜。そして、そのやさしく可憐な色合いは、多くの人の心をとらえて離しません。
そんな桜色を、自分の手で再現できたら素敵だと思いませんか?
この記事では、初心者の方でも安心してチャレンジできる「桜色の作り方」をステップごとにご紹介します。
絵の具や色鉛筆、水彩など、使う画材ごとに最適なレシピやテクニックをまとめてお届け。
色の基礎知識から応用のコツまで、丁寧に解説していきます。
ふんわりとした桜色を自分らしく表現して、イラストや作品に春の息吹を吹き込んでみましょう!
桜色の作り方

桜色とは?
桜色とは、春に咲く桜の花びらのような淡くてやわらかいピンク系の色を指します。
日本の伝統色の一つでもあり、優しさ・上品さ・儚さを象徴する色として、多くの文化やデザインに取り入れられてきました。
古典文学や和服の色名にも登場するほど、長い歴史と深い意味を持った色です。
一般的には赤系の色に白を多めに加えることで作られ、どこか透けるような透明感と、肌なじみの良さが魅力。
見た目の美しさだけでなく、心にやさしく寄り添うような心理的な落ち着きも与えてくれます。
桜色を作るための色の作り方一覧
桜色を作るにはいくつかの方法があり、目的や雰囲気に応じて使い分けることができます:
- マゼンタ+白:透明感のある軽やかな桜色。春の空気を思わせる清涼感が特徴。
- 赤+白+黄少量:少し温かみを感じる柔らかい印象の桜色。夕方の桜や逆光のシーンに合います。
- ピンク+茶色微量:落ち着いたトーンで、大人っぽさやヴィンテージ感を出す桜色。
どの組み合わせでも、白の量が多くなるほどやさしく繊細な印象に。
加える色の順序によってもニュアンスが変わるため、試し塗りをしながら調整するのがポイントです。
人気の桜色レシピ
おすすめは「マゼンタ:1+白:4」の割合。
これだけで、かなり桜らしい色になります。
そこにほんの少しだけ黄色を足すと、やわらかい春の陽ざしのような温かみがプラスされ、よりリアルな桜の色に近づきます。
さらに、発色の良い水彩絵の具を使うと、透明感を失わずにふんわりした印象が出せます。
チューブの赤を直接使うのではなく、薄めてから重ね塗りすることで、花びらのような軽やかさを演出することもできます。
桜色の完成例
完成した桜色は、花びらやリップカラー、春物の洋服や雑貨など、様々な場面で活躍します。
例えば、ほんのりくすみを加えた桜色は大人の女性にも人気。
ペールピンクやコーラルピンクと組み合わせて使うと、季節感を上品に表現できます。
また、イラストで使えば、春の背景やキャラクターの衣装などに自然な季節感を出すことができます。
さらに、和菓子のパッケージや季節限定のアイテムなどにも多く使われており、幅広い応用が可能です。
桜色を作るための材料

必要な絵の具と色鉛筆のセット
- レッド(カーマインまたはマゼンタ)
- ホワイト(チタニウムホワイト)
- イエロー(ほんの少し、温かみ用)
- オレンジまたはピーチ系カラー(彩度のバリエーション調整用)
- グレー(くすみを出したいときに便利)
桜色はほんの少しの色の違いで印象がガラリと変わるため、微調整用の色をいくつか用意しておくと便利です。
特に白は多めにあると安心。
使用頻度が高いので、大容量のチューブをおすすめします。
色鉛筆で再現する場合は、「パステルピンク」「コーラルピンク」「ホワイト」に加えて、「ベビーピンク」「ピーチ」「グレージュ」なども揃えておくと、混色や重ね塗りでより繊細な桜色が表現できます。
重ね塗りの際には力加減が大切で、柔らかく塗り重ねることで、発色と透明感を両立させることができます。
水彩絵の具と色鉛筆の違い
水彩絵の具は、色のにじみや透明感が活かせるので、桜のやわらかい表現にぴったりです。
少量の絵の具とたっぷりの水を使えば、淡く広がる桜色のグラデーションが手軽に作れます。
また、紙の質や水分量によっても仕上がりが変わるため、試行錯誤の中で自分の理想の桜色を探す楽しみもあります。
対して色鉛筆は、細かいタッチや重ね塗りができるため、花びらの縁の細い線や中心の濃淡など、繊細な描写に強みがあります。
レイヤーを重ねて質感を調整しながら、自分好みの桜色を丁寧に作り上げていく工程は、非常に創作意欲をくすぐるものです。
桜色を作るための3原色の紹介
赤・青・黄の三原色からでも桜色は十分に作れます。
まず赤(カーマインやマゼンタ)と白を混ぜて基本のピンクを作り、そこに黄をほんの少し加えることで温かみをプラス。
逆に、少量の青を足せば、クールで落ち着いた印象の桜色になります。
重要なのは、混ぜる順番と分量のバランスです。
赤をベースにし、白を加えて明度を調整。
さらに、黄や青をほんのひとさじずつ加えながら変化を確認していくことで、柔らかくも深みのある桜色が完成します。
この三原色ベースの方法は応用範囲が広く、自分好みにアレンジしやすいのも魅力です。
桜色を作る具体的な方法

マゼンタピンクを使った混ぜる方法
- パレットにマゼンタを少量出す。チューブからそのまま出すのではなく、筆先で少しずつ取りながら調整するのがおすすめ。
- 白を4〜5倍加えてよく混ぜる。このとき、均一になるまで混ぜるよりも、少しまだら感を残すと、塗ったときに自然な濃淡が出て美しく仕上がります。
- 色を見ながら微調整。黄色をほんの少し足すと温かみのある春らしさが強調され、青を極少量足すとくすんだ大人っぽい印象に変化します。目的のイメージに合わせて、何度かテスト塗りをしながら進めると安心です。
- 必要に応じて水で薄めて明度調整。特に水彩の場合は水分量のバランスで色の透明感が大きく変わるので、筆に含ませる水の量に注意して塗り重ねていきましょう。
- 混色後に、試し紙で一度乾燥させてから確認すると、実際に仕上がる色味を把握しやすくなります。
白なしでの桜色作り
白がないときは、代わりに水を多く含ませて色を薄める方法が効果的です。
特に透明水彩では、水を使って色を引き延ばすことで、自然な明度の桜色が再現できます。
ベースとして淡いピンク系の絵の具(ローズピンク、パーマネントローズなど)を使用し、薄く何度か重ね塗りすることで、ふんわりとした雰囲気を保ったまま、立体感のある色味に仕上がります。
塗り重ねることで発色が整い、白がなくても十分に桜のやさしさが表現可能です。
ピンクと茶色の組み合わせ
ピンクだけでは少し物足りない…というときは、茶色をほんの少し加えるとナチュラルで深みのある大人っぽい桜色になります。
特にバーントシェンナやローアンバーのような赤みのある茶色を使用すると、より柔らかくて落ち着きのあるトーンに仕上がります。
これは夕方の桜や落ち着いた背景色として使うと、シーン全体に温かみと奥行きを加えることができます。
また、ピンクと茶色を層として塗り分けることで、グラデーション効果も演出可能です。
仕上げにホワイトを薄く重ねると、光が当たったような透明感も加わり、よりリアルな花びらの風合いになります。
水彩で作る桜色

水彩絵の具を使った桜色の描き方
- 薄く溶いた赤系の絵の具を塗る。まずは薄いピンク系の色を作り、軽く湿らせた紙の上に広く伸ばしていきます。
- 水を含ませた筆で周囲ににじませる。塗ったばかりの部分に水を含ませた筆で触れることで、絵の具がふんわり広がり、自然なグラデーションが生まれます。
- 乾かしてから、白や黄を重ねて調整。ベースが乾いたら、薄い白や黄をそっと重ね塗りして、光の当たり方や花びらの立体感を表現します。
- 必要に応じて、細筆を使って中心に濃い色を加えたり、周辺に影色を加えるとリアルな仕上がりに。
水彩特有の「にじみ」や「ぼかし」が桜のやわらかさにぴったりです。
にじみを活かすことで、均一な色では表現できない“儚さ”や“繊細さ”を演出できます。
筆圧の変化や水の量によっても印象が変わるので、何枚か試し塗りをしながら感覚をつかんでいくのがおすすめです。
水彩の特性を活かした桜色作り
透明感を出すには水の分量がカギ。
絵の具を濃くしすぎると透明感が失われてしまうため、少しずつ色を重ねることが大切です。
色を乗せすぎず、筆に含ませる水の量を調整して、何度かに分けて重ね塗りしていくのがコツです。
また、紙が乾いている状態と湿っている状態ではにじみ方が変わるため、「ウェット・オン・ウェット」や「ウェット・オン・ドライ」といった水彩の基本技法を組み合わせて使うと、より表現の幅が広がります。
実践!桜色の花びらを描く方法
- 水を多めに含ませた筆で花びらの形を描く。まずは輪郭をはっきりさせず、やわらかい曲線で花びらの形を描くようにしましょう。
- 中央にやや濃いめの桜色を乗せる。中心から外側に向かってグラデーションを作るように、筆の力を少しずつ抜いていきます。
- 自然なグラデーションで、ふんわりとした花びらに。乾かす時間を調整することで、にじみ具合をコントロールできます。
- 最後に、影になる部分にごく薄いグレーや黄土色を加えると、桜の立体感がさらに増します。
仕上げに、白いハイライトを少し加えると光を感じる花びらになります。
光沢感を表現したい場合は、白を不透明なガッシュに切り替えて使うのもひとつの方法です。
まとめ
桜色は、一見シンプルに見えて、混ぜ方や使い方によって印象が大きく変わる奥深い色です。
この記事では、基本的な絵の具の組み合わせから、色鉛筆・水彩の使い方、さらにはデジタルツールを使った色シミュレーションまで、初心者でも実践しやすいステップで紹介しました。
色の再現は何度もトライする中で精度が上がっていくもの。
まずは今日紹介したレシピを参考に、実際に自分の手で“桜色”を作ってみてください。
少しずつ自分好みの色に近づけていく過程も、色作りの大きな楽しみです。
そして、完成した桜色をぜひ作品に活かして、春のやさしさや生命力を表現してみましょう。
色を通して季節や感情を描く楽しさが、きっとあなたの創作活動をさらに豊かにしてくれるはずです。