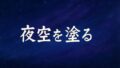みたらし色は、日本の伝統的な和菓子「みたらし団子」にかかっている甘じょっぱいタレから着想を得た、非常に魅力的で奥行きのある色合いです。
この色は一見シンプルな飴色に見えますが、よく観察すると橙から赤茶にかけての微妙なグラデーションが存在し、光の当たり方や見る角度によってツヤや透け感が変わるため、思わず食欲をそそられるような不思議な美しさを持っています。
また、みたらし色は単なる食品を思わせる色味だけでなく、私たちの心に温かみや安心感を与える心理的な効果もあり、和モダンなデザイン、ファッション、ネイルアート、さらにはブランドのコーポレートカラーとしても幅広く活用されています。
この記事では、そんな「みたらし色」を徹底的に掘り下げ、その特徴やデジタル・アナログ両面での具体的な作り方、イメージを膨らませるための応用テクニックなどを豊富な例とともに詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、単に色を再現するだけでなく、みたらし色が持つ繊細なニュアンスをあなたの作品やプロジェクトに活かせるようになるはずです。
みたらし色とは?

みたらし色とは、日本の伝統菓子みたらし団子にかかっているタレのような、光沢と透明感のある赤みを帯びた飴色のことです。
橙から赤茶系を基調としており、見る角度や光源によって微妙にニュアンスが変化するのが魅力です。
食欲をそそる色であると同時に、温かさや懐かしさ、和の落ち着きを感じさせる効果があります。
イラスト、ネイル、パッケージデザイン、インテリアなど幅広い場面で人気のカラーです。
色の深い特徴
- 色相:一般的にH35°前後の橙〜赤茶寄りの色域に位置し、少し赤みを強めることでより食欲を刺激します。さらに赤みを加えることで果実感や暖かさを増すことができます。
- 明度:中〜やや高明度(V80-90%)で、強く光を受けると透明感が増し、ツヤが引き立ちます。細かなグラデーションをつけるとより自然なみずみずしさが表現できます。
- 彩度:S50-60%程度を目安にしつつ、艶出しや陰影の描写では彩度を上げ下げして変化をつけます。部分的に彩度を落として深みを出すことでリアルさが増します。
- 代表的な近似HEX:
#E5B36E,#D0884E,#BB763F,#A76D54など。複数の色をブレンドし陰影をつけることでよりリアルに、また細やかなハイライトを入れることで一層立体感が増します。
みたらし色の階調を使い分ける

Caramel Sauceパレット( #FFD9BB – #FDC192 – #E2A06C – #D0884E – #BB763F )は、タレの透け具合や焦げ具合を段階的に表現するのに最適です。
これをさらに7〜8段階に増やすと、光の屈折や滑らかなグラデーションが再現しやすくなります。
また、細かい階調を重ねることでより複雑な色の深みや照り返しを演出でき、みたらし特有の艶っぽさを強調できます。
例えば背景や影部分に近いブラウンを追加したり、ハイライト付近にオレンジ寄りの明るい色を差し込むことで、一層リアルで魅力的な仕上がりになります。
デジタルカラーとしての活用例

| 色名 | HEX | RGB | CMYK | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|---|
| Light | #FDC192 | 253-193-146 | 0-25-43-0 | ハイライトに使うと光沢が増し食感が出る。周囲にぼかしを入れるとより立体感が増す。 |
| Base | #E2A06C | 226-160-108 | 0-29-52-11 | メインカラー、UIや商品パッケージにも適用可。濃淡を調整して背景や中間色にも活用。 |
| Deep | #BB763F | 187-118-63 | 0-37-66-27 | 焦げ色や陰影、アクセントに使うと引き締まる。微細な模様や縁取りに使うと高級感が増す。 |
これらを組み合わせて、ライトとディープの間にさらに数段階のグラデーションを加えることで、和菓子店のWebサイトや、食品系アプリで「食欲をそそるUIデザイン」により豊かな深みを持たせることができます。
また、グリッドやアイコンに少しずつ濃淡差を持たせることで奥行きを演出し、より高い訴求効果を生み出します。
絵具・レジン・ネイルでのみたらし色作り

不透明絵具(アクリル・ガッシュ)
- 黄土(6): 焦げ茶(2): 黒(1) の黄金比で混色すると、安定したみたらし色が作れます。さらに微量の赤やオレンジを加えて微調整し、白を加えれば明るく柔らかいみたらし、黒を少し増やせば焦げ寄りにできます。塗り重ねやドライブラシでテクスチャを出すのも効果的です。
透明水彩や色鉛筆
- 下地に黄みの強いオレンジを淡く塗り、その上に赤茶を重ねることで透ける層の重なりを表現します。さらにウォッシュやリフティングでムラを作ると、自然でみずみずしい仕上がりに。
レジンやジェルネイル
- 透明ベースに黄土+茶+極少量の黒を混ぜ、薄く乗せるとまさに「みたらしネイル」。光を通すと艶と奥行きが際立ちます。トップコートに少量のゴールドやラメを混ぜると高級感も演出できます。
応用アイデア

- イラスト・食品サンプル:立体物では黄土+茶+黒にクリア剤を混ぜる「タレレジン」が定番。これに少し赤やオレンジを混ぜて照り感を強調するテクニックもあります。さらにハイライトを部分的に強めるとよりリアルです。
- ネイル・ファッション:2025年も“みたらしネイル”が流行継続中。涼しげかつ温かみも演出し、ゴールドのラインやストーンを合わせると上品で華やかになります。浴衣や和小物との相性も抜群です。
- パッケージ・ブランドデザイン:自然素材や和テイストを打ち出すブランドのキーカラーにぴったり。さらにみたらし色を濃淡で複数配置し、背景や文字、縁取りに段階的に使うと高級感と奥行きが出ます。
記事のまとめ
みたらし色は単なる飴色以上に、光・透明感・濃淡のバランスで魅力が大きく変わる色です。
デジタルならHEXやRGBを複合的に使い分け、絵具やレジンなら6:2:1の比率を軸に好みで調整します。
さらにグラデーションの幅を増やしたり、微細なハイライトや色の重ね塗りを工夫することで、より深みやリアルさが増します。
心理的に「美味しそう」「安心する」印象を与える色なので、作品やプロダクトで積極的に取り入れると温かみのある印象がぐっと増し、見る人の記憶にも残りやすくなります。
こうした色彩の演出はブランディングや販促の面でも大きな効果を発揮します。